藤慶之
藤氏は美術ジャーナリスト。京都新聞社の元美術記者。
藤慶之 精密描写を楽しみながら-安田謙のリアリズム世界- 「安田謙作品展 1989」カタログから
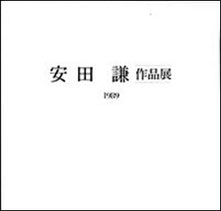
下記の引用部分は、1989年の個展の際に作成された図録の解説として書かれたもの。
関時之助氏の解説が主に1980年より前の、静物画を描き出す以前の安田謙の活動に重点を置いているのに対し、藤慶之氏の紹介はそれ以降の活動に焦点を当てて書かれている。対象とした時代による作者・作品像の違いだけでなく、両者の視点の違いに、それぞれのヤスケン像が浮かび上がる。
私が美術記者になった当時、安田謙氏は「ドン・キホーテのヤスケンさん」と言われていた。毎年秋の独立美術展になると、お伴のサンチョを連れて馬にまたがり槍をもって風車に突進する正義漢ドン・キホーテの図が、シリーズとして登場していた時期である。1960年代といえば、美術界はまさに抽象全盛の時代。安田さんの描くドン・キホーテも馬も、時代相の投影か、表現主義的な粗いタッチで単純抽象化され、諧謔を内に秘めながら、文学性と造形性との格闘が続いていた。70年代に入った頃から、作風は次第に写実的になり、登場人物や周囲の風景が精密に描写されるようになってくると、劇的な画面構成に不自然な違和感が見え始めてきた。
折しも、全国の大学に吹き荒れた学園紛争の嵐。京都美大教授だった安田さんも、学生たちの矢おもてに立って苦労した。1977年、12年間の美大づとめを定年退官した頃から、「ドン・キホーテ」シリーズは姿を消し、変わって宋元画を思わす劉生ばりの精密静物画が登場してきた。私は「ドン・キホーテ」シリーズ以前の仕事を知らないし、精密描写の静物画に移っていった動機についても聴いたことがないため、長い間、一種のしこりにも似たものが残っていた。
今回、静物画を中心にした近作個展と画集刊行を機に、画風変遷の胸の内を披露してもらい、そのわだかまりも少しは消えた感じだ。若き日、バロックの美術史家として知られた洋画家・須田国太郎氏に師事し、その影響を受けて、中世美術からルネッサンスをへてバロックと、ヨーロッパ・リアリズムの流れを吸収してきたせいか。
「初期の(注:若い)頃は、自分にとって対象をどれだけ写実的に描けるか、ということが目的でしたね。…(略)…最後には若き日からやりたかった写実へ戻ってきたようなもの」
という最近の心境には、自然体の作画姿勢が感じられる。安田さん自身、「諧謔小説的主題」と語ったこともある「ドン・キホーテ」シリーズ自体が、写実回帰の過程で不自然な主題に思えてきたのだろう。細密描写の深みに入り込めば入り込むほど、登場人物の表情も馬のポーズも、さらには周りの建物も家具類も、ぎこちなく反発し合って、画面全体の統一感を損ないかねない。それよりもドン・キホーテという騎士道修行物語を、写実描写することに、果たして意味があるのか。作者自身の中で大きな疑問が生じていた時期ともいえよう。
幸か不幸か、美大づとめを終えた頃から、酒豪で鳴らした安田さんは体調を崩し、病気がちとなる。体力にまかせて大画面に挑み続けてきた往年の作が姿勢に微妙な変化が生じても不思議ではない。ドラマ性の強いドン・キホーテの代わりに、アトリエの中に放置したままの骨董品や日常雑器など身辺雑記的な世界を「気力を取り戻す精神集中の手だてとして」描き始めた。
近年の静物画に描かれているのは、縄文、弥生、李朝の古陶から、トルコのガラス器、さらにはペルシャの更紗、ゴブラン織,丹波木綿まで、いずれも内外の骨董屋で蒐集してきたコレクション類。それに仏手柑やザクロ、柿、花などが添えられる。一見、スーパー・リアリズムやフォト・リアリズム絵画と思われがちだが、もちろん写真に頼ることはない。執念ともいえる凝集力で対象に迫り、微妙な明暗による精密描写でモノの質感まで活写した写実の跡だ。岸田劉生ら草土社の画家たちが追求した精神世界とは、体質的にも一線を画しているが、古裂に覆われた卓上に並ぶ古陶磁類や果物が、それぞれ独自に存在しながら互いに響き合い、寂境の空気を漂わす。
昨年のうち半分は入院生活を繰り返したが、昨秋の独立美術展には病院から抜け出して200号の大作に挑み、会員としての役目を果たしたが、無理がたたって今年の正月には再度入院するはめになった…という。それでも最近では午前、午後の3時間はアトリエに閉じ込もり、もの言わぬ静物たちと集中的に対峙し、精密描写の作業に没頭する。初期の「労働者」シリーズから「馬のシリーズ」、「ドン・キホーテ」シリーズへと14,5年間の周期で画風変遷の跡を残してきた安田さんに「そろそろ精密描写の静物画に飽きた頃ですか?」と水を向けてみたら、
「周期的には変わってもいい頃だが、不思議に飽きないのね。モノの質感や相互の力関係、周りの空気を表現することの楽しさ。もう、これは、趣味みたいなものだね」という自然体の答え。年とともに枯淡の境地に入っていくタイプの画家は少なくないが、「ヤスケン」さんは自らの持ち味でもある執念深い体質を楽しむかのように、まだまだマニアリスティックな絵筆を走らせることだろう。
(美術ジャーナリスト)
